昭和57年度(1982) を紐解く
- 晴夫 沼澤
- 2025年2月10日
- 読了時間: 2分
続けて紹介していきましょう。
昭和57年(1982年)度、スタートの4月号はこんな記事から始まっていました。

これは冠婚葬祭を特に取り上げていますが、「物」から「心」へという字句に、当時から、いわゆる物質文明に対する危機感は高まっていたのだなあと思わされます。
同じ号に、ごみ収集の話題もありました。

そういえばその頃はトラック運搬でした。「不燃物」「可燃物」という言葉も一般的になりつつありました。
社会の発展に伴って、現在の細かい区分ができたわけですが、「物」に頼ることはなかなか捨てきれていないという現実も表していると言えそうです。
誘致工場に県外からの研修生が来ているという記事がありました。

今は県外、国外との交流は、個人的なつながりに支えられていることが多いようですが、当時だとこうした形が一般的だったのでしょうね。
懐かしく思い出す人もいるのではないでしょうか。
この年度、何号か続けて話題にされていたのが「水道週間」の作品でした。

町内の小中学生に応募してもらい、たくさんの作品が集まり、絵や書写、作文など様々な紹介がされていました。
10月号の表紙にのった記事です。

こうしたユニークな取り組みをしながら、切磋琢磨していったということだと思います。貴重な資料ですね。
年が変わった正月の号では、五つの中学校、六名の生徒からの年頭抱負です。

もう五十代後半になっている方々かと思います。
あの頃描いた町の姿、どの程度実現したのでしょうか。
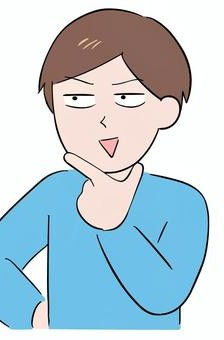


コメント