昔話12「化物退治」
- 晴夫 沼澤
- 2025年9月11日
- 読了時間: 2分
「羽後の昔話」は、第12話です。
非常にオーソドックスな題名ですが、昔語り風に発音すれば「バゲオノタイジ」となることでしょう。
お話は「泊まる所を探している村を通りかかった者が、化け物が住みつく荒れ寺などに行って退治し、そこに住むようになる。めでたしめでたし」とよくある筋ですが、様々なパターンがあります。
我が町の噺では…通りかかったのは「武芸者」で、出てくる化け物は「大ぐも」となっています。
今回は、最初からの紹介でなく、途中から侍が寺に入り寝入ったあたりから、引用してみます。
だんだん夜もふけで、十一時ごろ十二時ごろになったば、カランコロンカランコロンって下駄この音するずおの。
カラカラど戸あげで、おそろしく美しいあねさん、こうして重箱たがえで入って来たど。
「これ、わずがだども、あがってたんせ」って、黙って居たば、
「まだあどで、重箱もらいに来るんすがら」って、置えで行ったど。
「なえ持って来たおだべ。」
なえが入ってだが、あげで見でえべ、あげるどてこうして、手こ重っこのふたさかげだば、手がぴだーっとくっついでしまったど。
それでこんだな足かげで、その手とるどしたば、足もくっついで、手も足もくっついで、四つんばいみでえになって、ごろごろど転んで歩いてもなんぼしたたて、それとしれねえでよ。
そうしてるうち、奥のほうでガサガサガサガサど、何がはって歩ぐような音こするずおの。

と、ここから「大ぐも」の登場。侍との戦い場面になるわけですが、侍の持っている刀は、世に名高い名刀「村正」であり、その「柄」に彫られていたのが・・・・・
こんな展開を見せて、無事にハッピーエンドとなります。
お寺や社には、化物や怪物が棲みつく話は数々あります。
これは信仰の裏返しと言ってもいいでしょうし、人々が神秘なるものにオソレを抱いてきた証しでもあるように感じます。
何でも科学的に証明されるという考えもありますが、人知を超えた存在を認めたり、そうした歴史を尊重したりすることも、価値は大きいのではないでしょうか。
そうでなければ、それこそ人間が「化物」になってしまいます。



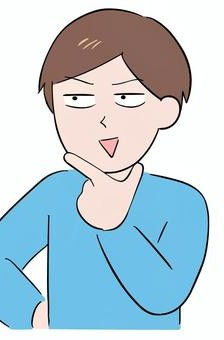


コメント