「羽後町の伝説」を読む(その13)
- 晴夫 沼澤
- 2025年2月20日
- 読了時間: 2分
「羽後町の伝説」もいよいよ残りもわずかとなりました。第13回目です。
上到米の甚助さんと並んで、義民の誉れが高い貝沢の名左エ門さんの話が「義民・名左エ門物語」として、なんと23ページにわたって収録されています。
くわしくは伝えきれませんので、あくまで概略だけという形ですが、紹介いたします。
今から二百年ほど前、貝沢で大工の棟梁をしていた名左エ門は、村の貧しさを救うために、村はずれにある高い丘を切り開き田んぼを作ろうとした。
初めは反対した村の仲間たちも、名左エ門の熱心さにほだされ話し合いをすすめる。そして、流れてくる水をせき止める貯水池を作り、水の力を利用して丘に上げる計画を立て、図面を作り上げた。
しかし役人に願いでたら、逆におこられ、前より高い年貢をとられることとなった。名左エ門は自分たちで工事をするしかないと決意し、村人の賛成を得てこっそり工事に取り掛かった。大変な頑張りを続け三年で完成させ、村人たちは手を取り合って喜び合った。
ところが、村人の中に名左エ門は田んぼをひとり占めしようとしているという噓のうわさを流し、役所に密告した者がいた。役所は名左エ門にはりつけの刑を言い渡した。それを知った名左エ門は、一人そっと家を出て、田んぼのあぜ道にむしろをしき、お経をとなえ、そして「ああ、ありがたいことだ。これでわしの仕事は終わった」とつぶやき、ふところから取り出したノミを、ぐぃとのどに突き刺し自害した。

重罪人の汚名を着せられていた名左エ門だが、わが身を捧げて地域のために尽くした功績は、人々の手によって様々な形で残されている。
非常に無念な事ですが感動的な筋書には違いありません。
詳細な事実はともかく、時代的には貧しさにあえぐ農民、そして取り締まる役人という構図があり、また村の結束もどこかで崩れる展開になることに、やや普遍性を感じます。
いずれ、新田開墾という史実は、名左エ門とともに行動した村の祖先たちによってなったものです。誇り高い歴史ですね。
さて一昨年(2023)11月に、三輪地区貝沢の皆さんにより発刊された冊子があります。
『貝沢誌』
秋田県羽後町 貝沢に生きた人びとの軌跡をたどる図書
『貝沢誌』調査研究編集委員会∥編齊藤 壽胤∥監修
貝沢部落会∥発行2023/10
羽後町には各地区それぞれの「地域誌」もあるわけですが、貝沢では独自に大変立派で、しかも内容の濃い一冊がまとめられました。
新聞等でも紹介されましたね。ぜひ、図書館等でご覧になってください。



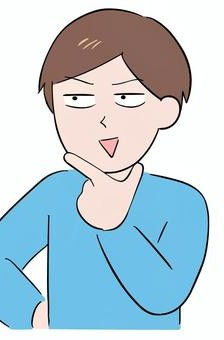


コメント