「羽後町の伝説」を読む(その12)
- 晴夫 沼澤
- 2025年1月31日
- 読了時間: 2分
伝説シリーズは昨年末にアップしてから足踏みをしていました。
今年最初は第12回目となります。
「吉三郎(きちさぶろう)の墓」という話です。
今回は、1ページ文なので「羽後町の伝説」に載っている全文を紹介いたします。
文章は小坂太郎氏です。

八百屋お七が駒込の吉祥寺の小姓の吉三郎に恋こがれ、一目会いたさに放火をしたのが広がり、明暦三(一六五七)年一月十八、十九日の江戸の大火事となった。
※1682,3年という説もあり。
お七は捕らえられて放火の大罪で刑死する。これが有名な振袖火事とよばれる伝説である。
さて、その後吉三郎は、自分に恋して放火し、最後に命を失ったお七の霊を慰めるため、一念発心して諸国行脚の旅に出た。
やがて羽後町三輪の吉祥院にたずねてきたというものである。
当時、糠塚に円福寺という寺があり、三輪の吉祥院の隠居寺といわれていたが、そこで生を終えた。墓碑に「祐泉」という号、元禄十六年という文字が刻まれている。
かつてこのあたりに「お七風邪」という感冒が流行したとき、この吉三郎の墓に参詣者が非常に多く霊験があったという。そこで、野ざらしのままになっていた石塔にお堂を立て現在にいたっている。

歌舞伎などの舞台で有名な「八百屋お七」のことが、なんとこの羽後町とつながりを持つとは意外でしたね。
ただし、よくあるように吉三郎(吉三)が亡くなって葬られたという話(墓がある)は、全国でいくつかあるようです。
諸国行脚であれば、こんなに遠くに来たとしてもおかしくはありませんね。
その絡みで「お七風邪」と名づけられた感冒があったという筋も面白いですね。
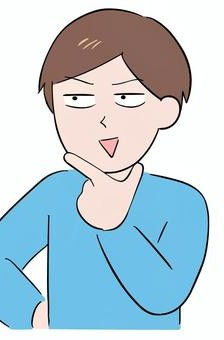


コメント